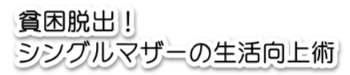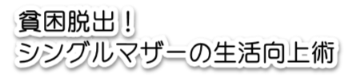2024年・令和6年度 高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)授業料支援

「高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)」(国の制度)について。
2010年から実施された高校授業料無償化の制度は、2014年4月から内容が変わり、「高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)」に変わりました。
高校授業料無償化の制度はその名のとおり、無条件で全ての高校生が無償でした。
しかし2014年の法改正で、一定の収入のある家庭は無償ではなくなりました。
2020年(令和2年)7月から資格判定の基準が変更になりましたので、これらも含めてご説明します。
目次
高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)について
平成26年4月1日以降の高校等(国公私立は問わない)入学者が対象で、世帯所得が一定額未満の場合、高等学校等就学支援金の支給を受けることで、授業料が実質無償になります。
なお、以下の「世帯目安年収」=両親・高校生・中学生の4人家族で、両親の一方が働いている場合の目安です。
令和2年6月まで
道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が507,000円(世帯目安年収910万円)未満である世帯
令和2年7月から(2024年・令和6年現在)
市町村民税の課税標準額に6%を乗じた額から市町村民税の調整控除の額を引いた額が304,200円(世帯目安年収910万円)未満である世帯
(※政令指定都市の場合は「市町村民税の調整控除の額×3/1」)
◆算出額が154,500円未満
(世帯目安年収590万円未満)
⇒国公立高校は基準額(年間118,800円、月額9,900円)支給。
⇒私立高校は年額396,000円(月額33,000円)まで支給。
私立高校授業料実質無償化の対象となります。
◆算出額が154,500円以上304,200円未満
(世帯目安年収590万円以上910万円未満)
⇒国公立高校も私立高校も基準額(年額118,800円、月額9,900円)の支給対象。
公立の全日制高校の場合、実質自己負担なし(=授業料無料)となります。
私立の差額授業料は自己負担。
私立高校の就学支援金
令和2年4月分(2020年4月)からは私立高校授業料無償化により、対象者は最高額で月額33,000円の支給が受けられます。
上記のとおり、算出額が154,500円未満の世帯であれば、年額396,000円(=月額33,000円)の支給対象となり、実質授業料が無料となります。
高等学校等就学支援金の支給を受けるには、申請が必要です。
市町村民税所得割額・道府県民税所得割額は何を見ればいい?
「市町村民税所得割額」「道府県民税所得割額」の確認は、
◆会社員の方は毎年6月頃に勤務先から配布される市町村民税特別徴収税額通知書で。
◆個人事業主の方は、毎年6月に市町村役場から送付される納税通知書で。
※上記それぞれの書類が手元にないときは、
◆市町村民税・県民税課税(非課税)証明書を市区町村役場で発行してもらいます。
または
◆マイナンバーカードの写し等
提出書類
★高等学校等就学支援金受給資格認定申請書
(各学校で配布されます)
★所得を証明する書類(イ~二のどれか)
ィ)特別徴収税額の決定・変更通知書の写し
ロ)納税通知書、課税証明書等
(市町村民税所得割額が記載されたもの)
ハ)生活保護受給証明書の写し
二)マイナンバーカードの写し等
(マイナンバーカードの写し、マイナンバーが記載された住民票等)
提出先と申請時期
★提出先
在籍する学校
★申請時期
入学時及び毎年7月頃
1年生のみ4月と7月の2回。
2・3年生は7月です。
※マイナンバーで所得要件を確認する場合は、一度書類を提出すれば追加の書類提出は必要ありません 。
支給限度額
支給額は学校の種類によって違います。
◆国立高等学校、国立中等教育学校の後期課程
・・・月額9,900円
◆公立高等学校(定時制)、公立中等教育学校の後期課程(定時制)
・・・月額2,700円
◆公立高等学校(通信制)、公立中等教育学校の後期課程(通信制)
・・・月額520円
◆国立・公立特別支援学校の高等部 ・・・月額400円
◆私立高校(通信制)・・・上限24,750円まで
◆上記以外の支給対象高等学校等(つまり公立私立全日制高校)
・・・月額9,900円
私立高校は算出額154,500円未満は月額33,000円までの支給)
※詳細は文部科学省HPの支給期間・支給限度額一覧をご覧下さい。
就学支援金の受け取りは?
就学支援金は学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料に充当しますので、直接支給されるものではありません。
なお、学校の授業料と就学支援金に差額がある場合(授業料>就学支援金)は、生徒本人(保護者)が足りない分を支払うことになります。
(学校によっては、一旦授業料を全額徴収し、後日、就学支援金相当額を還付する場合もあります)。
詳しい事、わからないことは こちらへ
↓ ↓ (文部科学省の公式サイトです)
★公立高等学校における就学支援金(新制度)の問合せ先
★私立高等学校における就学支援金(新制度及び旧制度)の問合せ先
★高等学校等就学支援金(新制度)Q&A
尚、授業料無償化の『就学支援金制度』の他に、授業料以外の教育費の負担軽減のための『高校生等奨学給付金制度』があります。
『就学支援金』と『奨学給付金』の違いの解説↓
まとめ
高等学校等就学支援金制度(高校就学支援金)は、
- 国の制度である。
- 保護者等の市町村民税の課税標準額×6%-市町村民税の調整控除額が304,200円未満未満の世帯が支給を受けられる。
(※政令指定都市の場合は「市町村民税の調整控除の額×3/1」) - 各学校で配布される「高等学校等就学支援金受給資格認定申請書」と「所得を証明する書類(課税証明書など)」を学校に提出する。
- 申請時期は、入学時及び毎年7月頃
- 支給額は国公立高等学校(全日制)は月額9,900円。
- 私立高校場合は、世帯の所得に応じて月額33,000円または9,900円の支給となる。
- 就学支援金の受け取りは、生徒本人ではなく、学校が受け取り授業料に当てる。
- 学校の授業料と就学支援金に差額がある場合の不足分は、生徒側が支払う。